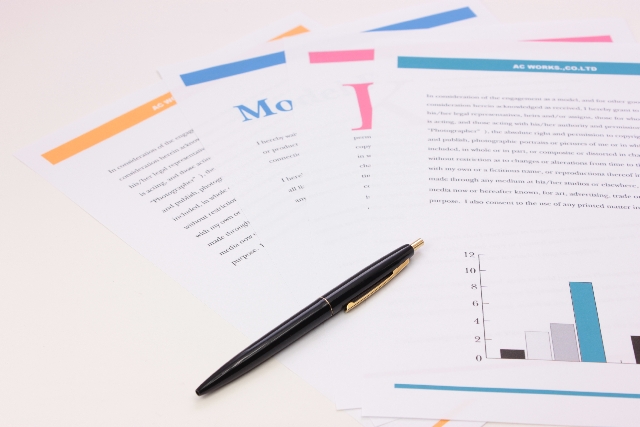


失業保険と年金について。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。
退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。
退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
まず、社保の扶養になっているのであれば、ご主人が保険料、年金を負担しているわけではありません。あなたが扶養になってもならなくてもご主人の支払う金額は変わりません。
社保年金の扶養には失業手当も収入とみられますので、日額が3611円を超えているのであればご主人の社保の扶養にはなれないです。ご主人の会社に確認してもらって、会社の指示に従って下さい。
社保年金の扶養には失業手当も収入とみられますので、日額が3611円を超えているのであればご主人の社保の扶養にはなれないです。ご主人の会社に確認してもらって、会社の指示に従って下さい。
退職・休職の保険
長文になります。
現在、先月の流産のショックで精神的に不安定です。
睡眠がとれない、食欲がない、頭痛、吐き気、胃痛、体力がない、急に泣き出す、手が震える、顔見知りでない人が怖く冷や汗がでる。等の症状です。
メンタルクリニックにはあさって行きます。
約半年勤めた仕事は辞めずに営業という業務ではなく事務・雑務で労働時間を短くしてもらうか、一時休職して復帰をするかを検討していて、店長より上の上司にその旨を相談していました。
上司は病院の結果と体調をみて最善な方法を考えればいいと、言ってくれました。
ただ今月から異動してきた店長にも報告をしたところ、営業ができないならどの店舗にも席はない。仕事辞めれば専業主婦じゃん。うらやましい。辞めるなら人を募集しなきゃいけないんだから早く言ってね。と冗談まじりで言われました。
体調のいい日だったので一応笑って答えていましたが、次の日から仕事に行くのがとても嫌になりました。
店長に会うのも話すのも嫌です。
今月から店長になって店の売上やら張り切ってるのはわかりますが…傷つきました。
婚約者も理解がない店長の下で私を働かせたくはないと思ってるみたいで、退職をすすめています。
私も今では早期退職か休職を考えています。
もし、病院で働くことができないと診断された場合は、退職後にも傷病手当てなるものがもらえますか?
休職のほうが今後のことを思うといいですか?
働くことができると診断された場合は退職したら求職をしてさらに3ヶ月後にしか失業保険がもらえないんですよね?
詳しい方ご教授下さい。
今の会社の前はアルバイトですが1年社会保険に加入していました。
文章がうまくまとまらず、さらに愚痴が入ってしまい申し訳ありません。
長文になります。
現在、先月の流産のショックで精神的に不安定です。
睡眠がとれない、食欲がない、頭痛、吐き気、胃痛、体力がない、急に泣き出す、手が震える、顔見知りでない人が怖く冷や汗がでる。等の症状です。
メンタルクリニックにはあさって行きます。
約半年勤めた仕事は辞めずに営業という業務ではなく事務・雑務で労働時間を短くしてもらうか、一時休職して復帰をするかを検討していて、店長より上の上司にその旨を相談していました。
上司は病院の結果と体調をみて最善な方法を考えればいいと、言ってくれました。
ただ今月から異動してきた店長にも報告をしたところ、営業ができないならどの店舗にも席はない。仕事辞めれば専業主婦じゃん。うらやましい。辞めるなら人を募集しなきゃいけないんだから早く言ってね。と冗談まじりで言われました。
体調のいい日だったので一応笑って答えていましたが、次の日から仕事に行くのがとても嫌になりました。
店長に会うのも話すのも嫌です。
今月から店長になって店の売上やら張り切ってるのはわかりますが…傷つきました。
婚約者も理解がない店長の下で私を働かせたくはないと思ってるみたいで、退職をすすめています。
私も今では早期退職か休職を考えています。
もし、病院で働くことができないと診断された場合は、退職後にも傷病手当てなるものがもらえますか?
休職のほうが今後のことを思うといいですか?
働くことができると診断された場合は退職したら求職をしてさらに3ヶ月後にしか失業保険がもらえないんですよね?
詳しい方ご教授下さい。
今の会社の前はアルバイトですが1年社会保険に加入していました。
文章がうまくまとまらず、さらに愚痴が入ってしまい申し訳ありません。
>もし、病院で働くことができないと診断された場合は、退職後にも傷病手当てなるものがもらえますか?休職のほうが今後のことを思うといいですか?
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば受給出来ます。
1. 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
また、退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
1 退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
休職して、傷病手当金を受給してから退職し、引き続き傷病手当金を受給すれば、良いと思います。
>働くことができると診断された場合は退職したら求職をしてさらに3ヶ月後にしか失業保険がもらえないんですよね?
自己都合退職となり、失業給付を受けるには、3か月の給付制限期間が課されます。
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば受給出来ます。
1. 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
また、退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
1 退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
休職して、傷病手当金を受給してから退職し、引き続き傷病手当金を受給すれば、良いと思います。
>働くことができると診断された場合は退職したら求職をしてさらに3ヶ月後にしか失業保険がもらえないんですよね?
自己都合退職となり、失業給付を受けるには、3か月の給付制限期間が課されます。
失業保険の給付制限があるかないかによって健康保険をどれにしたらいいのかわからないので教えてください。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。
又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?
わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。
又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?
わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。「健康保険」は総称ではありません。民間サラリーマンが加入する公的医療保険の名前です。
・任意継続というのは、ルールとしては2年間止められません。
保険料を期日までに支払わなければ追い出される形で止めることになりますが、それを利用するのはあくまでも裏技です。
〉わかるものでしょうか?
離職理由によります。
「正当な理由のない自己都合」なら給付制限があります。
「会社都合」か「正当な理由のある自己都合」なら制限はありません。
〉先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。
「同じような」であって、「同じ」ではなかったからでしょう。
離職票の書き方一つで判断は変わります。
また、たとえば結婚退職のような場合、結婚と退職との間隔によって判断が違います。
※具体的な離職理由を書いていただければ助言しようもありますが書いてないのでその点には踏み込みません。
〉給付制限90日
「3ヶ月」です。
・任意継続というのは、ルールとしては2年間止められません。
保険料を期日までに支払わなければ追い出される形で止めることになりますが、それを利用するのはあくまでも裏技です。
〉わかるものでしょうか?
離職理由によります。
「正当な理由のない自己都合」なら給付制限があります。
「会社都合」か「正当な理由のある自己都合」なら制限はありません。
〉先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。
「同じような」であって、「同じ」ではなかったからでしょう。
離職票の書き方一つで判断は変わります。
また、たとえば結婚退職のような場合、結婚と退職との間隔によって判断が違います。
※具体的な離職理由を書いていただければ助言しようもありますが書いてないのでその点には踏み込みません。
〉給付制限90日
「3ヶ月」です。
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
①退職金以外の収入に対しての住民税額になります。
②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。
③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。
旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。
④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。
基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。
③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。
旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。
④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。
基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
関連する情報